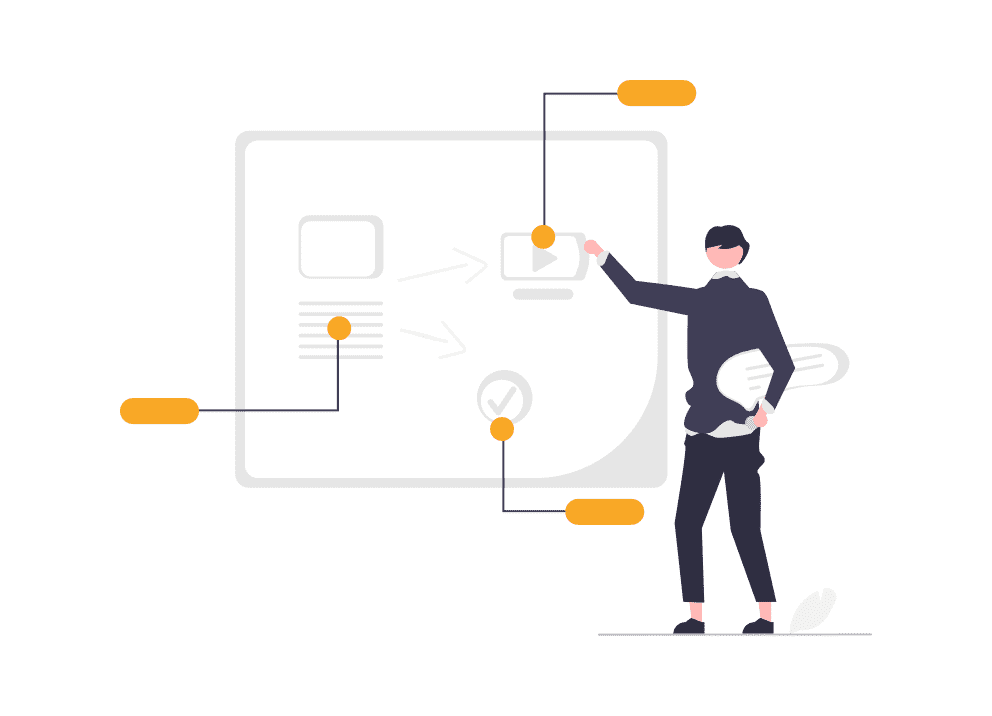専門用語でしか話せないようではダメ
技術者に限ったことではないが、その道の専門家でない人に専門用語でとうとうと説明する人がいます。
専門用語をしっかり説明した上ならまだしも、専門用語でしか説明できない人もいるから困ります。
特に相手が上司や部門長であっても、自分と同じ専門的理解をしているとは言えません。
ましてや別の組織の人や経営層の人に説明するのに、専門用語を使って説明しても相手には伝わりません。
いかに専門用語を使わずに説明するか、というのは日頃からやっておかないとできません。
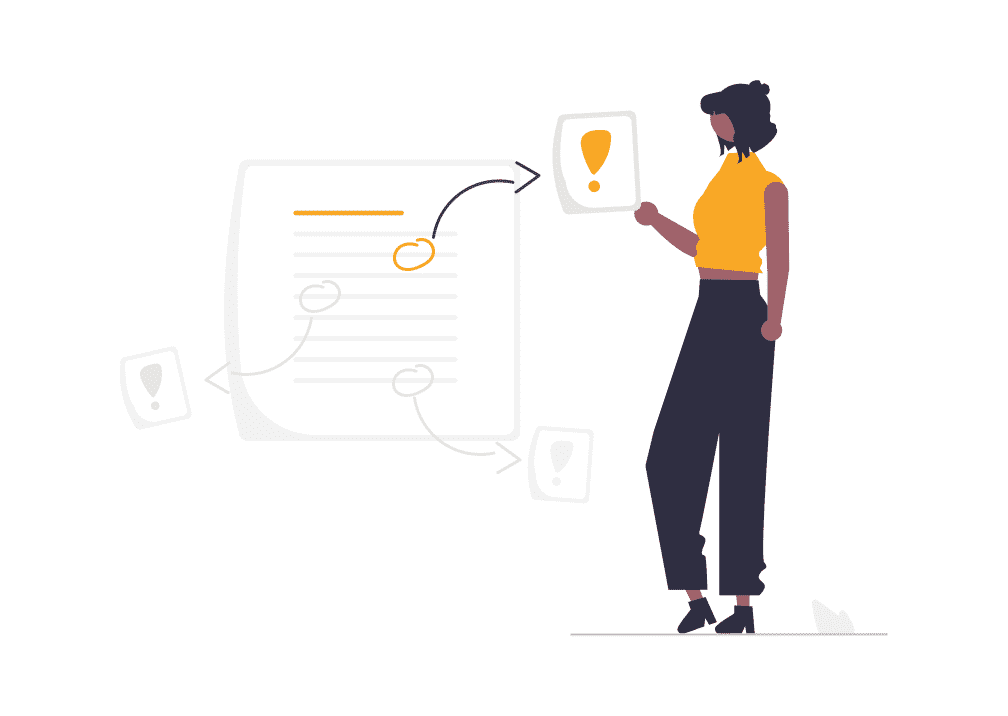
専門用語を使うことで何を伝えたいか?
どういう言葉が専門用語でしょうか?
ソフトウエアの世界でいうと、一例ですがビルドとかバッチなどのソフトウエア開発のプロセスに関するものや、UMLであるとかJavaScript/Pythonといった名称もそうでしょう。
その道の専門家同士で話しするなら、専門用語の方が間違いはないし話しが早いので、それで良いです。
ところが、非専門家に話しをするなら、専門用語を使わずにもっとわかりやすい言葉で話すべきです。もしかすると、その用語を使った話しをする必要もないことだってあります。
大事なことは、その専門用語(あるいはそれをわかりやすくした言葉)を使うことで何を伝えたいのか?ということです。
JavaScriptを使うことが必須の条件だから、JavaScriptをバリバリ使えるエンジニアが必要だ!と訴えたいなら、JavaScriptを全面に押し出す必要があります。
ところが、これこれのシステムをこういう仕様で作ります、と説明する際に「開発言語はJavaScriptでバックエンドでもフロントエンドでも使える便利な言語で開発します」という説明をしようとするなら、この説明がそもそも必要か、ということを考えるべきです。
なぜなら、聞く人が何らかの判断をしなければいけない立場の人ならば、JavaScriptを使うということに自分はどう判断すればよいか迷うからです。
その人に判断をしてもらう必要があるなら、JavaScriptとは何でどういうメリットがあるかを説明する必要がありますし、そうでないなら説明は不要なのです。
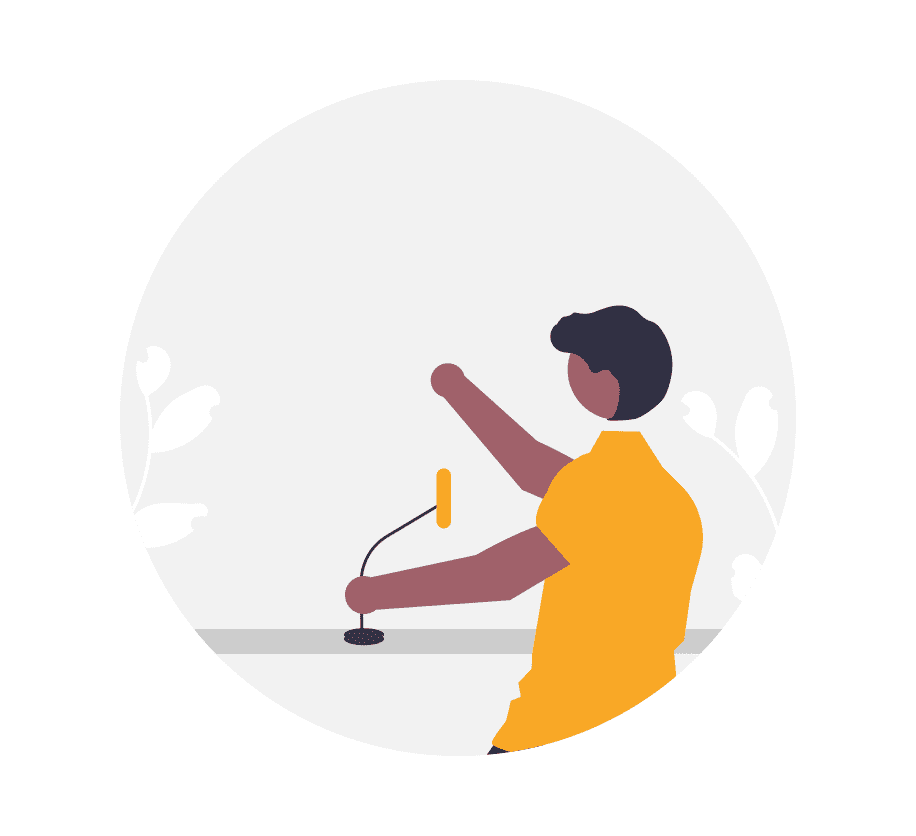
カタカナ用語を安易に使うのは聞き手に失礼
専門用語だけではないが、経営層もすぐに旬な英語を使いたがります。
- フィジビリティ(実現性)
- アサイン(任命)
- イシュー(論点・課題)
- オルタナティブ(代替策)
- ジャストアイデア(思いつき)
などなどあげればきりがないのですが、僕は括弧内の日本語の方がはるかにわかりやすいと思っています。
なぜカタカナ用語を使うのかわからないことも多いです。
ネットの時代とはいえ、聞きながらわからない用語をスマホで検索するわけにはいかず、知ったかぶりで聞くことになります。
聞き手にそんなことをさせるのではなく、誰もがわかる言葉で話すべきだと思います。
それができないのは聞き手への配慮が足りないと思います。

専門用語をわかりやすい言葉に置き換える
専門用語をそのまま使わないようにするためには、その言葉の意味を別のわかりやすい言葉に置き換える作業が常日頃必要になります。
ソフトウエアの中でも説明しにくいのが、アーキテクチャやフレームワークなどがあります。
アーキテクチャは「ソフトウエアの論理的構造」という説明が見つかりますが、ソフトウエアにおける「論理的」というのも非専門家には理解が進まないものです。
時と場合によりますが、僕はアーキテクチャを「全体の構成」と説明することが多いです。
もう一つのフレームワークは、ビジネスでも「考える仕組み」のような意味で使われるので言葉としては浸透していますが、ソフトウエアにおけるフレームワークは機能や仕組みを持っているものを指すので、似ているけれどもビジネスで使うフレームワークの理解だと少々違うと思います。
ソフトウエア開発におけるフレームワークは、ソフトウエアを効率的に開発する仕組み、などと説明すると良さそうです。
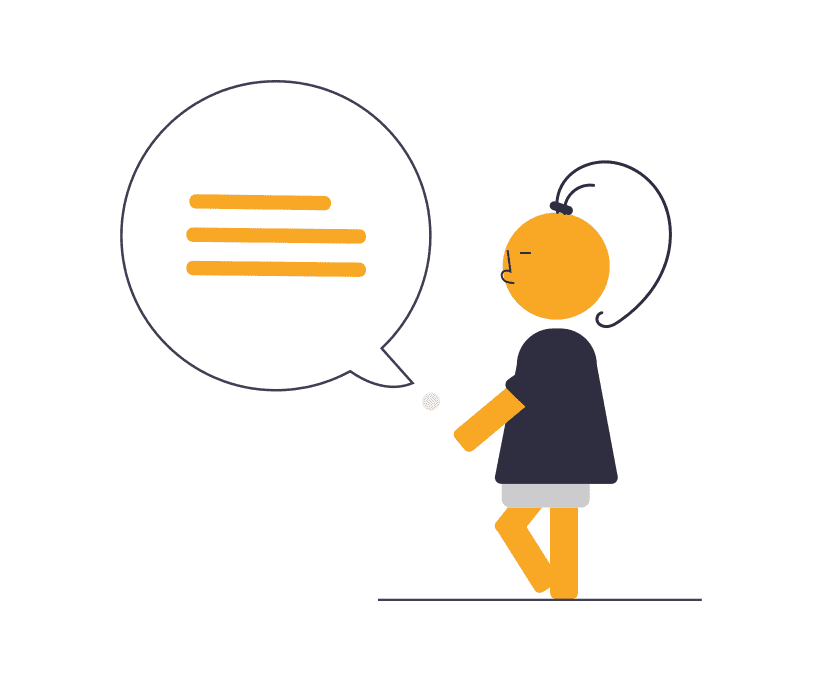
難しい言葉を使わずに説明する事が大事
人に伝えるためには、専門用語を使わないことがいいですが、そうすることでそれ以外の部分もわかりやすくなります。
なぜかというと、どうやって専門用語を使わずに伝えるかを考えることは、ひいては説明のわかりやすさにつながるからです。
単に専門用語を少しわかりやすい日本語に置き換えたところで、それだけでは説明がわかりやすくなったとは言えないことも多いです。
専門用語を使わないでいかに伝えるか?ということを考えていくと、説明が人に伝わりやすくなります。
その人が持つ専門性を考えながらバランスよく考えていく必要はありますが、難しい言葉を使わずに伝える、これが大事です。